選択したカテゴリの記事一覧
×[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

シェイクスピアの初期の時代劇・復讐劇『リチャード3世』読みました。
きっかけは、いくつかの本でリチャード3世がアナロジカルに使われているのを見て、読んでおこうというまじめなものです笑
世界史の資料集をひっぱりだしてきて、プランタジネット朝、ランカスター朝、ヨーク朝の関係や血統の復習もしておきました笑
ちなみにリチャード3世はヨーク家。
なんというか展開がすごくはやく、時間がたつのを忘れて読んでしまった。
敗れたランカスター家とチューダー家のいがみ合いと、ヨーク家内における内紛が、「呪い」という基本旋律で描かれている。
夫と息子をリチャードに殺害されたランカスター家のマーガレットとヨーク家の掛け合い、夫エドワード4世が病死し、3人の息子(弱冠で殺害されたエドワード5世含む)と弟をリチャードに殺害されたエリザベスと、そのエリザベスの娘をめとろうとするリチャード3世の掛け合いが、言葉遊び、含蓄にとんでおり、テンポのよいもので唸らせるものがあった。このシーンはお気に入りであるし、当作品の見せ場でもあると思う。
一方で権謀術数のマキャべリストであるリチャード3世、びっこでせむしというが、その策略たるや、おそろしく冷酷。
自らが王位を手中に収めようと、腹心に身内を殺させるよう指示するが、その腹心までも裏切り、殺害する。
めでたく、王位につけたものの、自分の意見にすこしでも躊躇するものを自分の地位を危ぶむものとして、今まで腹心であろうと、ばっさり殺してしまうのであるが、
そこには、自分が容易に人を裏切っていたように、自分も計略によって裏切られるのではないかと、人を信用できず、猜疑心にさいなまれた王を哀れなものだという印象をもったが、その私の感情そのものも、私が良心をもつもであるがゆえであり、リチャードからいわせれば、良心は小賢しい足かせ、それは弱者の所有物なのである。
彼は亡霊の呪いにより、自らの罪を後悔し、懺悔を始めるかと思いきや、良心を臆病者だと断じ、自らが高みを目指すための権謀術数を妨げる、煩わしいものとして退けるのである。
最終的にリチャード3世はのちのヘンリー7世であるリッチモンドに殺されることで「復讐」が達成し、エドワード4世の娘エリザベス(リチャードが求婚?した)と結婚し、ランカスター家とヨーク家は和合し、チューダー朝(ヘンリー7世の父はリッチモンド伯エドモンド・チューダー)の治世の開始で本劇は終わるのである。
解説にもあったように、本作品ではさまざまな人物が殺されるが、劇中で実際に殺害シーンが演じられるのは、クラレンス公(リチャード3世の次兄)とリチャード3世のみである。
クラレンス公は劇のはじめに、リチャード3世は劇の終わりに殺害されるのが、劇に対象性を与えるものとなっている。
ああ、生きた人間のかりそめの愛顧を、神の恩寵にもまして、懸命に追い求めるあさましさ!
他人の笑顔にひたすら希望をつなぐ男は、マストの上に酔っ払った舟乗りも同然、舟が揺れるたびに、いつ放りだされて、深い水底に引き込まれるかしれたものではない。
これはリチャードに裏切られた腹心のヘイスティングズの嘆きである。
王位継承の内紛に、身内忠臣関係なく、明日いつ誰が自分の敵になるやもしれなぬという、悲劇を如実にあらわしているように思う。
PR

久々の更新です。
ドストエフスキー長編『カラマーゾフの兄弟』を読みました。
俺的に『罪と罰』よりかは読みやすいかなとは思ったけど、そこで著者が論じていることは当時のロシア社会、とりわけ知識人階級が先導したところによる、大きな問題の核となる部分を鋭い考察したもので、テーマとしてしては『罪と罰』よりかはより広範で、より普遍性を持った問題なのではないかと思った。
それの概要について、俺がこの場で説明し、自分の意見を披露するには、今一度当該箇所を読み直し、色々検討するという作業が必要だが、今ひとつそのような技量そしてそれをなしえる時間を当方持ち合わせていないゆえ、割愛するが、それにまつわるほんの印象の紹介と、べつに俺の個人的な論点から『カラマーゾフの兄弟』を解題(かなりおおげさだが)してみたいと思う。
ロシアは地理的にヨーロッパに使い分、といってもペテルブルクやモスクワに限ってだが、絶えず影響を受けてきた。
本作品を読んでいると、わが母なる大地ロシア、といったような表現に見られるように、ロシアという広大な土地と、ロシア人として民族意識が不可分に結びついており、解説にもそれが「スラブ的」と書かれてあった。
ロシア正教という価値観のもとで培われてきた「ロシア的」なものが危機に瀕している。
というのは、ロシアの知識人階級の多くは、ヨーロッパ的なもの、とりわけフランスの思想の影響を強く受け、「自由」「平等」という観念の虜になっていた。
民衆は相変わらず「ロシア的」であり、正教を重んじてはいるが、社交界などでは、「新しい思想」に大きな期待をよせるものたちの様子が描かれている。
ヨーロッパ的な価値観と従来のロシア的な価値観の葛藤の中、多くの知識人は無神論的、共産主義的なイデオーグに染まっていくこととなる。
とりわけ、次兄イワン・カラマーゾフはこの典型である。
それに対して、末っ子のアリョーシャは修道院の見習い僧(?)で旧来のロシア正教の価値観をもつ「神がかり行者」として描かれている。
しばし、この二人は神の所存、認識をめぐって、(イワンの「大審問官」は特に有名でこれが本書の核にあたるともいわれる)、激論を交えている。
当のドストエフスキーはというと、アリョーシャの意見が彼のそれに当たると思うのであるが、『罪と罰』の結末よろしく、キリスト教的価値観、つまり民衆がロシアを救うと考えている。
詳細は省略するが、
進歩主義的な価値観と全体主義的な土着のキリスト教的価値観の相克、互いに相反する大きな価値観がぶつかり合うダイナミズムが、それぞれのそれぞれに対する議論の要がわかりやすい形で、鋭く語られ、描かれている様子が読んでいて実におもしろかった。
私自身は、キリスト教を信じているというか、それにすがって生きているものなので、ものすごく精神に応えた箇所でもあったが、その辺について、精神的に優れた時期に、読み直し、自分の意見を述べることにしたいと思う。
長兄のドミートリ・カラマーゾフについて、もっぱら、彼は「カラマーゾフ的」だとされる。
彼は、自分の気高き信念をとことん固執し、貫く高潔さ と同時に、それが破滅への道に至るとわかりつつも、それを自己破壊の道を選らんでしまう
というアンビバレントな性格をもつ青年として描かれている。
父のフョードル・カラマーゾフの放蕩さも持ち合わせてはいるものの、気高き率直さ、神聖的ともいえる高潔さを同時に持ち合わせているのだ。
このアンビバレントな感情は、つまり、自分に関わるあらゆる道徳的義務を全うしたいと願う思いと自己が破壊することを受け入れ、一種の自己破壊に伴う陶酔、というアンビバレントな感情は誰しも多少は持っているのではないか。
全人類のために理想高く、志を燃やし、そのための道徳的義務も自ら引く受けるとする気概。
これはあらゆる人が持つのではないか。
私に言わせれば、この感情の強い人間のうち、身近な日常の道徳的義務をなおざりにするようなもの、つまり、普遍性のためになら、理念のためになら、命もかけるか、具体性にはそっぽを向くという人。
これは案外日常多く見かける気がする、例えば国際ボランティアをして、恵まれない人のために自分の一生をささげたいという志を持ちつつも、実際ボランティアにいって「今」それをすることを避けようとし、仮にしても、精神すり減らしてこんなんと思ってなかったという、今に生きず理想を生きるもの。
一方で、自己破壊的行動。
それを、放蕩を「カラマーゾフ的」な血のせいだと正当化し、知らぬ間に父と同じ徹を踏むという、
いやむしろ「血」というのはそれが自己破壊的なものであれ、卑劣漢なものであれ、恐ろしく心理的な安定をもたらせる。
それゆえ、自ら自己破壊的な行動をとるというドミートリは、単純に、自己破壊的行為への憧れという程度の差こそあれ誰しも持っているであろう心理的特徴に一義的に還元すべきではなく、そこにはなまぐさい血のもたらす効果も加味されるべきであるというより、それが第一義的であるとすら思う。
私の個人的な血筋からも、ドミートリ・カラマーゾフのこのような傾向にいたく共感しながら読んだものであった。
この二つの心理的特徴をすべての人間が共有するのかいなかはわからないが、当時の退廃したロシア社会のひとつの表象として捉えるべきであろうか、それとも、ポストモダンを生きる現代において、何かしらの一般的特徴をもつ行動となって現れえるものとしての、観察すべき、普遍的なものと捉えるべきであろうか。
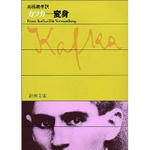
カフカの『変身』を読みました。
なんていうか、不思議すぎる!しっくりこないというか。
そもそも、朝起きて、自分が巨大な虫になってて、どうして、その理由を自問しないのかが謎。
(家族もだけど!)
何か、神によって裁きを受けるようなことをしただろうかとか、そういう発想はなく、虫に変身したために朝出勤できなかったが、周囲の人が自分の様子をみて、驚いたら、出勤できなかったことは、至極当然だと考えるだろうとか、全く驚かなかったら、次の汽車ででていけばいいのだ。って、心配するところちゃうやろー
一生このままなのか!?人間に戻れないの!?!?って焦ったり、絶望したりしないことを考えると、
この「変身」は案外、願ったりかなったりじゃないのかって思わざるを得ない。
主人公のグレーゴルは、今の仕事(外交販売員)は束縛が大きく、いつか自由な身になってやると考えていることからも考えて、この「変身」はそういった現状(現実ではない)からの逃避という意味合いがあるのではないか。
家族を養わなければならないという強い義務感と、もっと自由になってまともな精神状態をもちたいという感情が、この「変身」に繋がったのではないかと思う。
最後の「解説」を読むと、主人公と父親の関係も、絶対的な父親というイメージが本作品で見られることも指摘されており、様々な解釈があっておもしろい。カフカの人生を知り、他の彼の作品などを読むと、もっと深く、カフカの意図するところがわかるのかもしれない。
ま、別にドイツ文学の研究者になるわけでないのだから、厳密になりすぎてもおもしろくないので、さっきの「変身」=現状からの逃避という、俺の解釈(それが一般的かどうかなのかも知らないが)をもとに、何か考えたことをまとめておく。
グレーゴルはもともと家族思いで、家族のために懸命につくした。そんなグレーゴルを家族は愛した。
しかし、虫になってしまったグレーゴルに、嫌悪と愛の二律背反の感情で家族は揺れ動く。
働けなくなってしまったグレーゴルは、家にお金を入れることはできない上に、収入を得るための苦肉の策として迎え入れた下宿人を追い出してしまう。
家族はこれをきっかけで、我慢の限界に達し、グレーゴルという厄介者をどうにかしなければならないと考えるようになるが、翌日、グレーゴルは死んでしまう。
家族はいくら醜い虫となってしまっても、グレーゴルを愛していた。死んだとわかると家族みんな泣いたのだが、過去は過去と決別し、新たな生活へとささやかな希望を持つのである。
切ない感情を抱かずにはいられない。
グレーゴルに対する、愛と嫌悪の感情の相克も痛々しいほど伝わってくるが、
「変身前」あれほど、尽くした息子・兄は、もはや稼ぐこともなく、家族に害を及ぼすだけになってしまったことで、嫌悪が愛に勝り、見捨てられることになる。
結局、家族であっても、なんらかのプラスの役割(機能)を果たさなくなれば、そのかけがえになさは、死でもってしか再び、立ち現れてこないのであろうか。
つまるところ、人間は「孤独」なのである。
別の観点から。
仮に外交販売員という仕事という現状からの逃避願望が体現化して(中島敦の『山月記』みたく)、「虫」に「変身」したとしても、結局、家族をさらさら捨てる気にはない主人公は家族というひとつの呪縛からは解放されないわけ。
普段、こんな日常生活おもしろくないなー。もっと自由にならないかなー。いっそ部屋の隅においてあるクマのぬいぐるみにでもなれなたらなー楽やろーなーなんて、高校のときによく妄想したがが、
また、将来、自分の思うどおりに、何のしがらみもなく、自由に生きたいなーなんて考えたりするけど、
その妄想は、自分の周りにいる人たち、とりわけ家族の存在を想起することでいかにして容易く自分を現実に引き戻すか、それは誰しも経験があることだろうと思う。
自由になりたい、家族を幸せにしたいという相反する願望のうち、前者の実現のみが、調整されることなく無配慮に、押し付けられたとしたら、それは『変身』の筋書きになるのではないか。
虫になった主人公が感覚が人間離れしていく様子が示唆的である。
人間は、社会的存在の拘束性からは、逃れられず、拘束されている限りにおいて、人間の感覚を保持できるのであろう。
つまり、人間は、究極的に「自由」になれず、「孤独」な存在だということである。
『ガリヴァー旅行記』(中村好夫訳のやつ)読みました。
俺自身、バックパッカーで色んな国に行くのが好きなので、空想であるとはいえ、旅行譚には興味があったので、読みました。
「小人の国」と「大人の国」は、当時の英国の風刺も交えつつも、ファンタジー的要素が強くて、おもしろいです。
しかし、「ラピュタ島」から調子が変わっていき、「フウイヌム国」では徹底した厭人主義で、本作品に対するイメージがかなり覆されました。
小島「グラブダブドリッブ」では、魔法使いに過去の偉人たちを呼び出してもらい、対話をするのであるが、この場面が一番、おもしろくおもった。英雄の輝かしい功績が臆病の故の偶然であったなどの暴露や、時代の異なる大学者を話し合わせようとするなど、実におもしろい。
また次に「ラグナグ王国」では、不死人間が存在し、ガリヴァーはもし自分が不死だったら、長年にわたって蓄積された膨大な知識を活かし、国に貢献したいなどと妄想をするのであるが、そこにいた不死人間は、80を過ぎると理性を持った人間として認めてもらえず、契約を交わすなどのいっさいの法的な権利は剥奪されてしまう。老化とそれに伴う痴呆は人間を蝕み、周囲から厄介者扱いにされる。ガリヴァーの抱く妄想は、人間だれしもが不死ならばと思い描くであろうものであり共感できるのだが、死は人間にとって救済なのだとガリヴァーと共に思い知らされるのである。
最後の「フウイヌム国」で、一切の私情によらず、透徹した合理的思考にもとづいて行動する洗練された「フウイヌム」(馬)の治める国を訪問する。
彼らを理想化し、人間に似た身体的特徴をもち、醜い狡猾さをもつ「ヤフー」と人間の共通点を挙げ、人間のもつであろう醜さに絶望していく。
帰国後も、家族とともに食事することもなく、妻の体臭よりも、馬の臭いを好むなど、狂人じみた生活を送るようになるのだ。
最終章は読んでて、実に気分が悪くなる。最終的に、人間は凄まじく醜いものとして描かれた「ヤフー」以下として描かれるのである。
自分にも厭世的なところは大いに認められるが、ここまで徹底的にはなれないし、作者スウィフトの生涯を見れば、それがうなずける。本人が人間の汚さを持った野心家で、しかし、それを凌ぐ汚さを持った人間に打ち負かされた結果、自分も含めた人間全般を厭うようになったのであろう。
それにしても、後味の悪い作品だけれども、一級の風刺文学としてその座に君臨し続けるのは頷ける。

『ティファニーで朝食を』を読みました。これは去年の12月のレビュー、感想文です。
主人公の女の住所は「旅行中」
ハリウッドの与える栄光を拒否し、自由気ままに生きる女。
でもそれは、自分の居場所を見つける旅行の途中だから。
ティファニーで朝食を食べるような理想の場所を探す旅の途中だから。
読んでて思ったのは、まさに自分も旅行中だなと。
その日限りでもう会うことはなかったり、ちょっとした縁で友達になったり。
付き合っては別れ、別れては付き合っての繰り返し。
時にはそれに疲れ、嫌になりながらも、懲りずに恋をする。
みんな「居場所」を見つける旅人なんじゃないですかね。
空に浮かぶ一筋の浮雲のように、僕らは夢みて、どこに流れていくのか。
彼女は、名前を付けていない猫を逃がしてしまうのですが、すごく後悔をする。
悲しいかな、どんな自由な浮雲も一人悠然と流れるにはちと厳しいのかな。
としみじみモードです。
僕にティファニーで朝食を向かえられるときはやって来るのでしょうかね。笑
なんか、案外、恋愛系の純文学が好きだったり。笑
