×[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
社会学について漠然としたイメージしか持ってなかったのですが、本書を読んである程度、まとまったイメージをもつに至りました。
社会学の学問領域と諸分野を系統立てて紹介していて、入門書としては最適かなと思います。
特に日本における社会学の研究および社会学史が充実していて、欧米の思想に偏ったものではないのが、特徴だと思います。
著者の富永先生はパーソンズの研究者だったらしく、全体的にパーソンズ的な機能主義的な考えを重視しているなというのは読んでいてわかるので、彼のセンスというか、好みが反映されているなということは念頭において読んだほうが無難でしょう。
ミクロ社会学についての記述も基本的にいかにマクロ社会学と接点をもつか、結びつきうるかという観点で書かれている部分も多く、また総じてミクロ社会学についての記述が少ないので、それについては別の本で読むべきだと思います。
俺自身は、哲学と社会学に興味があるので、おのずと社会学も、ミクロ社会学的なアプローチが自分の性に合ってるなというのはかねてから思っていたから、あまり社会システム理論は好きではないんだけど、ルーマンの「複雑性の縮減」の考えはおもしろいなって思った。
実証主義か理念主義か。
社会学と哲学に進むものにとって葛藤になるのは、専門コースとしては社会学に進むものにとって、問題はここだと思う。現象学的社会学のような思弁的なものばかりやってるわけにはいかないんだろうなあ。
あと、農村とかのフィールドワークとかしょうもないことやってる人多いけど、一体何なんだろうって思ってんだけど、農村社会学って社会学の正統な、いやもはや王道を行ってるものだとは知らなかった笑
理論社会学が王道だと思ってたけど、社会学史的に考えたら(特に日本の場合は)、案外そうでもないのね笑
いや、今まで社会学について、その体系について、自分の興味に即した断片的なものしか知らなかったけど、本書のおかげで、ある程度がっきりしてよかった。
説明も平易でわかりやすいし、寝る前にぼーっと読む程度でもすこぶる理解できるし、オススメの一冊である。
PR

竹内洋先生の『教養主義の没落』を読みました。
いろいろ感想があるんだけど、
まず、俺はあんまり日本の知識人、論壇について詳しくなかったので、歴史社会学的アプローチで教養主義やエリート学生文化が明らかにされていくうちに、特に大正、昭和初期のそれが概観されていて、とても勉強になった。
大正教養主義、マルクス的教養主義・左傾、軍部による弾圧、教養主義、マルクス主義の復活、全共闘による教養主義の攻撃、高等教育のマス化による教養主義の没落とサラリーマン文化への適応。といった学生文化を中心に、それがいかに移りかわっていったのか、明瞭に論が展開されていて、おもしろかった。
旧制高校から帝国大学という学歴貴族における「旧制高校的」文化と、新制高校や私立大学や非帝大における「新制高校」的文化の狭間をいきた文化人の葛藤やせめぎあいも、わかりやすかった。
帝大文学士とノルマリアンの比較もブルデューの理論が使われていて理解しやすく、岩波書店の果たした役割等々、目下のところ(日本で)学者になろうと考えている自分にとっては、知っておくべき事実であろうと思う。
という本書全体の概説的な感想はそれまでにして、本書で「教養主義者」と呼ばれているものが、まさしく自分にあてはまるものだと思い、読んでいて、はらはらさせられるものがあった。
本書86ページに「教養主義とは、歴史、哲学、文学などの人文系の書籍の読書を中心とした人格主義である。」としている。それは修養主義的に読書されるものである。(「農村的」)
この点に関して、私は特に人文系の読書を通じて人格を完成させるという大義名分のもとで読書をしているわけではないものの、直接的な目的ではないが、結果的に意図せず導かれうるものである可能性をもつ、つまり読書の蓄積によって、自分の考えに「深み」が増すものであることは信じている。しかもそれは大衆文学ではなく、もっぱら、文学作品や哲学書を通じてでである。
しかも、それはまさしく、修養主義的に、耐え忍んでたくさん読むべきだと考えている点も共通するところがある。
さらに、帝大文学士の教養主義者が、「文学部」というひとつの「表象」、「ブランド」を誇りにする心理、すなわち、文学的なもの以外の不外部世界との隔絶、または超越を通じて、それらと差異化するという傾向がある。わたしは「パンのために」学問するのではないという自負が、学問、文学の道へと進むもののRasion D'etreを支えたのであろう。
私も常々、政治学や経済学、法学などの「実学」を軽視して、哲学や文学、理論社会学を重んじている傾向と一致しているし、「文学部的」なものに威厳を感じているし、「大学に入ったのは勉強するためであって、働くためではない」と家族に公言しているのと一致する。哲学書や文学作品の威信を信じてやまないし、なぜ多くの人は哲学を勉強しないのだろうかと疑問をこぼすほどである。
本書を読んで、自分は学生文化の正当な文化は教養主義的なものだと信じてやまなかった、ほかの大勢のものがそれから「逸脱」しているものだと信じてやまなかったのだが、現代の主要な学生文化からすれば、自分が時代錯誤的であることが判明したのである。勉学する自分、その際に自明視して疑わなかった教養主義を、客体視させてくれるきっかけを同書は与えてくれた。
しかしながら、本書に述べられているには、教養主義が学生文化の規範文化であったころ、たくさんの本を読んで、教養豊かであろうとすればするほど、それが成功者とされていたわけだから、そうでないもの、つまり、修養主義の中で、「修行のたりないもの」にとっては、象徴的暴力空間でありえたことにはうなずける。
それを転覆しようと、マルクス主義の文献のみを読むべきものとし、その他の哲学書を読んでいるものを「旧い教養」として蔑むのは、まさしく教養主義の転覆を図るものであるし、しかし、それがマルクス主義的なものの文献の読書を前提とし、西洋の一文化からでたものに礎を持っている点で、彼らが攻撃をしている大正的教養主義に依存関係あるのだ。
さらに、知的階級という階級がまだ明確だった全共闘時代における、その運動は、「団交」に教授を召喚して、無理難題をおしつけ、恥をかかせるという、教養主義への、特に学歴貴族のエリート主義に対するルサンチマンに基づくものである。
以上のように、学生は「教養とはなにか」「知識人とはいかにあるべきか」といったような問いを絶えず問い続け、煩悶としてきた中で、「教養主義」はさまざまな天秤にかけられることになった。
しかし、70年代以降、大学のマス化が進むにつれて、学生はそのような問いを立てなくなった。そのような問いを醸成させる精神的土壌は大学からはなくなった。
それゆえ、今日における、私のような「教養主義者」は教養主義そのものを疑うことを知らず、自明視する結果となったのである。なんとも恥ずべきことであると思う。
だからといって、現代の大学から自己を磨くこと、完成させることは消え去ったわけではない。
友人関係やバイトなどの人との交際からいろんなものを「キョウヨウ」として学ぶのである。
就職活動をしている人がどこどこに人事部にえらいさんがすごい、インスパイアされる云々たれているのを耳にして、それは就職に際する適応、一種の儀礼的なものさえ感じていたのだが、本書を読んで、それは人との交際いもまれることで、人文書から得るもの以上に、それをキョウヨウとして受容することに重きを置くキョウヨウの学生文化の、サラリーマン文化への適応という主流の文化装置によるものであるこという解釈をえ、多いに納得のいくものであった。
学生文化の移り変わりを、社会の変化とともに抽出した、自己を客体視させてくれる「教養書」である。
自己言及的で刺激的であった。
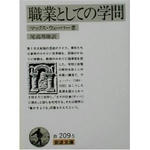
マックス・ウェーバーの『職業としての学問』を読みました。
今のところ、将来は学問を職業にしようと考えているので、タイトル見て、読んでおこうと思いました。
大学での教職につく難しさは、昔も今も変わらないのだなと。ドイツとアメリカの大学教員の採用の制度の違いや、徐々にドイツがアメリカ化してきて、昔ながらのドイツの教授と意見が合わなかったりした背景が興味深かった。
どの教官も自分が採用されたときのことは嫌な思い出で語りたくはないらしい。運やコネが大きな要因となっていたようで、自分よりも実力のある人たちを差し置いて、自分が採用されたり、正教授に昇進したりするのが、気のいいものではないらしい。
このへんのくだりは、前にとある他大学の准教授に酒の場で聞いた話と一致するので、官僚制でアメリカの大学の制度を取り入れた日本の大学であるが、この手の問題は大学という制度につきものなのであろうか。
自己を滅して、学問(職業)に専念すること。
学問の進歩は、自分の考えが常に時代遅れになる 宿命から発し、それを欲するところからはじまる。
教師は指導者になるべきではない
等々、もっと年を重ねてから読み返すと、違った読みができそうな箇所があって、また読みたいと思う。
この演説は、マルクス主義への傾倒、またはニーチェによる文化価値の喪失などの、現実の社会の否定という雰囲気のもとで、理想や体験、新たな世界観、指導者を欲した青年に向けられたものである。
「時代の宿命に男らしく堪える」ことをウェーバーは要求するのである。
そして、時代の宿命に目を伏せ、「大きな物語」を欲する青年に、ウェーバーが「日々の要求に従おう」といって講演を終えているのは印象的である。
学問は自らの前提を理論的に証明することはできない、ただ学問の限界内において事物を明確にすることが探求されるに意義があるのであり、生きる意味を与えてくれるものではないのだ。
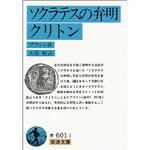
プラトン著『ソクラテスの弁明』『クリトン』を読みました。
特に前者は、倫理の授業でよく話した内容なので、読んでいてわかりやすかったです。
どちらも量も少なく、読みやすいので、手軽に読めます。
ソクラテスのように、知者、物知りだと自負している無知蒙昧な人に無知であることを自覚させ、学問の出発点であるべき「無知の知」という謙虚な態度にもっていこうとする、つまり啓蒙の人間はいつの時代も、自己反省をしない虚栄心や猜疑心の強い人間にとっては、高慢に見え、煙たがられる存在なのであろう。
ソクラテスが、自らの理性の示す道、また神の栄光によって導かれる道にのみ従うべきであり、それは今まで行ってきたように青年をはじめ多くのアテナイ人と対話することであり、国法がそれを止めるように命じるならば、それに従うことはできないとし、国法が死刑を命じるならば、それを受けようとした。
いや、自分の信じるところの真理に反することを、是が非でも貫徹させる態度、知行合一を貫くのは、哲人そのものであろう。
ただ、読んでいて思ったのは、論理の展開が類推によるものが多いのが気になったが、当時のギリシャではその手の論理の展開が常套手段だったのだろうと思った。
『クリトン』の対話篇でソクラテスを説得するクリトンとソクラテスとのやり取りがすごく面白かった。
善く生きること、美しく生きること、正しく生きること、はすべて同じことだという内容があって、すごく印象的だった。うん。
あと、ソクラテスの国家観(といってしまうと、国法との”対話”はプラトンの創作だろうから、純粋にソクラテスのそれとはいいづらいのはあろうが)に、ちょっと関心を持った。
図解雑学シリーズ『読みたくなる世界史』の12,13頁において、ソクラテスを告発した3人のうちの1人、アニュトスがアルキビアデスという青年をめぐって、ソクラテスと恋敵であり、その嫉妬心があり、そして彼がペロポネソス戦争でスパルタに情報を売り寝返った男であり、その師であり恋人であるソクラテスをその廉で糾弾したという隠された史実があるとかないか。笑
ソクラテスは、国家の認める神を信じず、青年を誘惑し害を与えたという理由で告発されたとなっているが。
古代ギリシャは同性愛が美しいもと最上なるものとされ、青年のギリシャ的肉体美がもてはやされた時代である。
実に開放的で羨ましい限りである笑

セーレン・キルケゴールの『死に至る病』を読みました。
高校生のときから実存主義思想に興味があったので、まずキルケゴールから。
絶望と罪の諸形態についての分類が興味深かった。
はじめにあるように、本書は「教化」と「覚醒」のために書かれたもので、中途半端なクリスチャンである自分にとって、読んでいて、とても重く、滅入るものであった。
「自己とは、ひとつの関係、その関係それ自身に関係する関係である。」
つまり、人間は「無限性と有限性」、「時間的なものと永遠的なもの」、「自由と必然」の綜合に関係する関係ということである。
そして、(絶望を自覚しているか否かを度外視して考える際、)この各々の関係項が一方のみに偏った場合に人は絶望するのである。
ここで、自分が陥っている絶望のひとつであろうと思ったのは、「無限性」に偏っていて、「有限性」を蔑ろにしていることに起因する絶望である。
キルケゴールは精神的な実存を本来的なものとする。
人間が自己の精神について反省し、その反省の度合いが強くなればなるほど、絶望の度も強くなり、罪の度も強くなる。しからば、神から最も離れた位置に行くことになるが、一方で神と最も近い位置にいるのである。
自己反省をせずに、自分が絶望していることに気づかないことのは、それに気づいているものよりも絶望的であるが、自己が絶望していることに気づき、自己自身であろうと欲しない、または欲する場合は、自ら絶望していることに気づかないものよりも、はるかに絶望の度は高いのである。
昔は、俺は、絶望して、自分自身であろうと欲していなかったのであるが、最近は、絶望して、自分自身であろうと欲する形態の絶望に陥っているように感じる。
キルケゴールのいう宗教的実存には後者のほうが近いのであろうが、単純に日々の”張り合い”というその点だけにおいていえば、前者のほうが、ある意味「人間的」なのであろうと感じる。当然、それは、キリスト者としての自己自身に無自覚になり、日常の雑多なことに埋没しているほうが、「直接的」で、絶望の度も低いので、そちらのほうが楽だといっているようなもので、当然、捨てられるべき感情なのであるが、自分の中には、そういうものへ堕落してしまうのではないかという恐怖があるのも事実である。
神の恩寵に対する絶望は、俺にとって、もっとも恐ろしい絶望であり、罪であるが、それを克服するためには信仰のみであることはうなずける。(俺はその種の絶望はしていないが)
神やキリスト、あるいは教説を概念的に把捉することは、不可能であるとするところ、問題は、ひとりひとりが単独者であり、倫理の問題は、ヘーゲル哲学の否定的な、一般化、普遍化の哲学・思弁では把捉されず、各々の具体性が問題とされると提起したところが、ドイツ観念論を乗り越える意味で、キルケゴールのした仕事で意義深いものなのであろう。
キルケゴールは「つまずき」をキリスト教的なものへの信仰の契機として、最後には3つの段階に整理して論じ、とても重要視している。しかし漠然とか「つまずき」について理解できなかったので、今後は、キルケゴールの「つまずき」の議論を追ってみたいと思う。
なお本書の内容については、以下が詳しい。
http://www.geocities.jp/enten_eller1120/text/kierkegaard/krankezumtod.html
